 不思議
不思議 昨日を持たないアパート
古い三階建てのアパートには、不思議な決まりごとがあった。住人は誰一人として、「昨日のこと」を覚えていない。朝になると、廊下ですれ違う住人たちは必ず同じ会話を交わす。「はじめまして」「ええ、こちらこそ」名刺を渡す者もいれば、照れたように会釈す...
 不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議 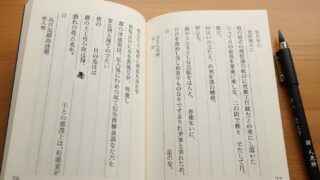 不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議  不思議
不思議