 不思議
不思議 呼ばれることで、透明にならない
名前を失うと、人は少しずつ透明になっていく世界がある。最初は指先からだ。光が指の輪郭をすり抜け、影が薄くなる。次に耳、肩、膝。最後に残るのは、胸の奥にしまわれた温度だけだと、人々は言った。この町では、生まれたときに与えられる名前を「錨」と呼...
 不思議
不思議  面白い
面白い  動物
動物  面白い
面白い  面白い
面白い  ホラー
ホラー  面白い
面白い 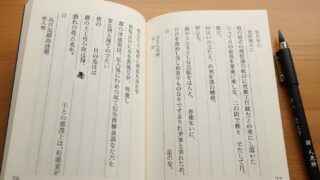 不思議
不思議  ホラー
ホラー  面白い
面白い