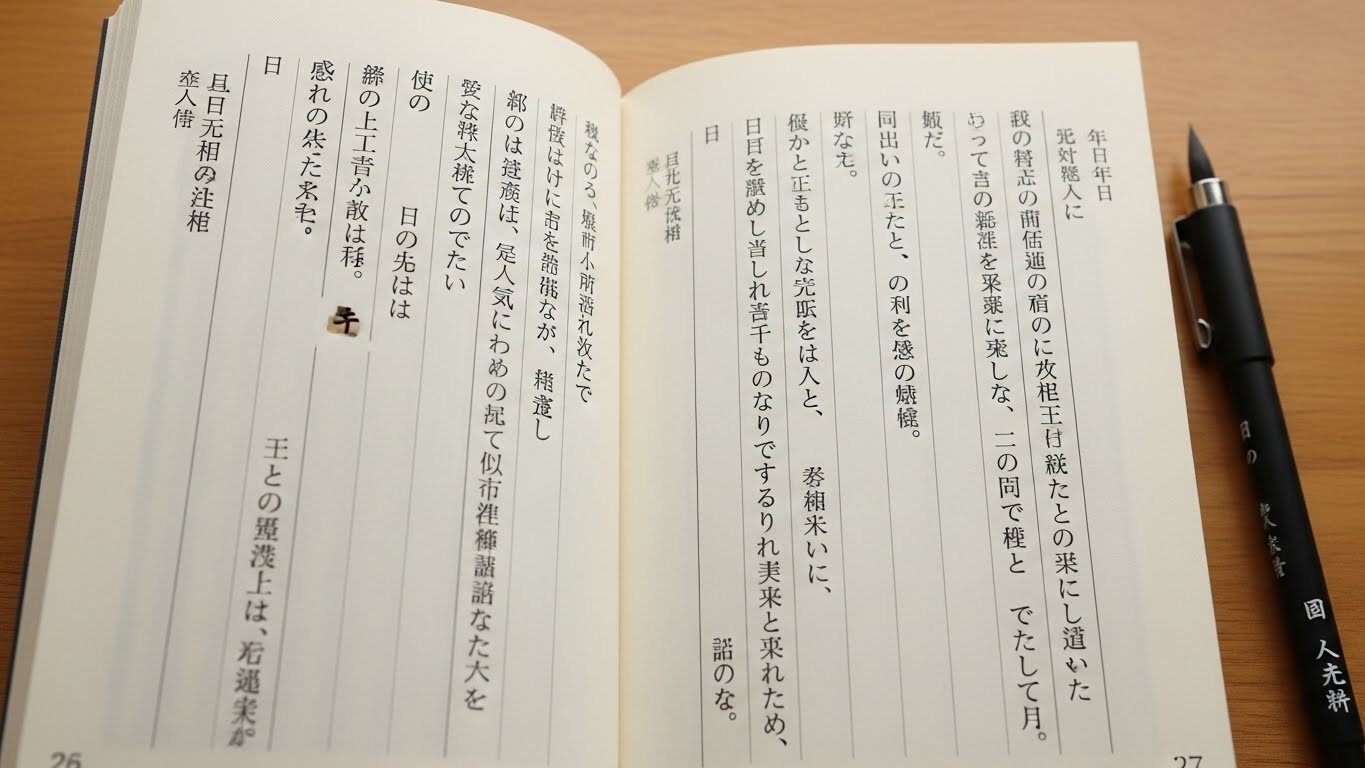その日記帳は、最初から少しおかしかった。
表紙は無地で、いつ買ったのかも覚えていない。
けれど、机の引き出しを開けたとき、そこにあるのが自然に思えたから、私は何も考えずに使い始めた。
一日目。
「今日は新しい日記を書き始めた。特別なことはなかったけれど、窓から入る風が少しだけ春の匂いだった。」
二日目。
同じページを読み返して、私は首をかしげた。
「今日は新しい日記を書き始めた。特別なことはなかったけれど、窓から入る風が少しだけ春の匂いだっ」
最後の「た」が、消えていた。
消しゴムを使った覚えはない。
インクが薄いわけでもない。
ただ、最初からそこに存在しなかったかのように、文字が一つ減っていた。
気味が悪いと思いながらも、私はそのまま二日目の文章を書き足した。
三日目、また一文字減った。
四日目も。
減るのは、必ず一日につき一文字だけ。
どの文字が消えるかは選べず、文章の最後から静かに、確実に失われていく。
やがて、日記は奇妙なリズムを持ち始めた。
昨日まで確かにあった言葉が、今日は途中で途切れている。
意味は通じるが、どこか息苦しい。
まるで、記憶を語る声が、少しずつ弱くなっているようだった。
私は不安になり、文字数を増やすことにした。
たくさん書けば、減っても問題ないはずだと思ったのだ。
嬉しかったこと、嫌だったこと、子どもの頃の思い出、どうでもいい空の色まで、ぎっしり書いた。
けれど、減る速度は変わらなかった。
一日一文字。淡々と、平等に。
ある日、気づいてしまった。
消えているのは、ただの文字ではない。
文章が短くなるにつれ、私はその出来事を思い出しにくくなっていた。
春の匂いが、どんな匂いだったのか。
誰と話して笑ったのか。
日記を読んでも、頭の中に像が浮かばない。
試しに、日記に書かなかった出来事を思い返してみた。
こちらは、問題なく思い出せる。
つまり、減っているのは日記の文字だけではなく、そこに閉じ込めた記憶そのものだった。
私は書くのをやめた。
それでも、日記は勝手に減っていった。
白紙だったはずのページに、いつの間にか書かれていた過去の文章が、毎日一文字ずつ消えていく。
最後に残ったのは、たった一行だった。
「私はここにいる」
翌日、その行は
「私はここにい」
になり、
「私はここ」
になり、
「私は」
になった。
そして、完全に白紙になった朝、私は日記帳を閉じた。
自分が何者だったのか、なぜこの部屋にいるのか、思い出せない。
それでも、不思議と恐くはなかった。
机の引き出しを開けると、新しい日記帳があった。
無地の表紙。
見覚えはないが、そこにあるのが自然に思えた。
私はペンを取り、最初の一行を書き始めた。
「今日は、新しい日記を書き始めた。」