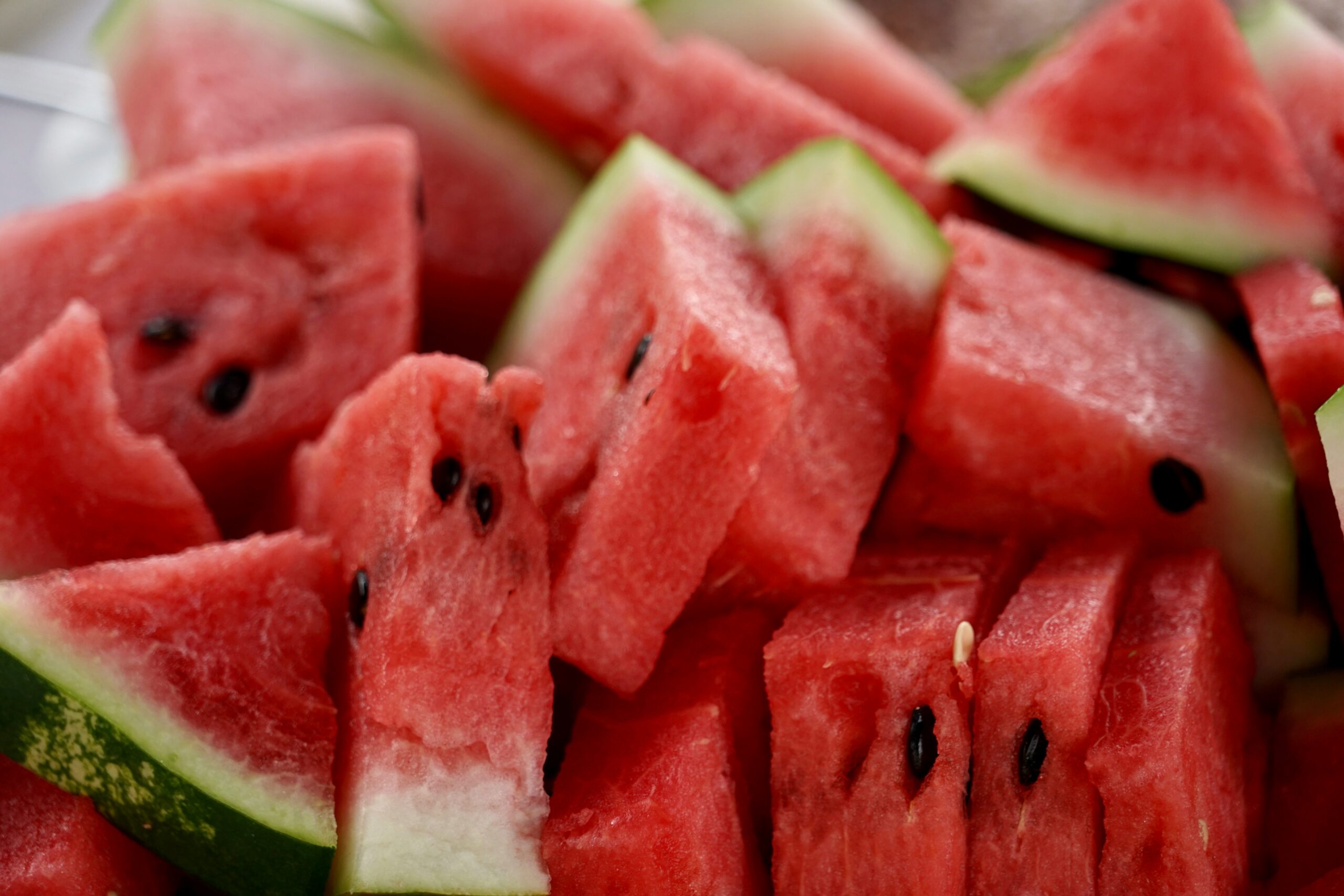「今年も、来たなあ」
六月の終わり、商店街の八百屋「山下青果」の店頭にスイカが並びはじめたとき、望(のぞみ)は心の中でそう呟いた。
スイカが出始めると、夏が本当に来た気がする。
汗ばむシャツと、昼間のセミの声と、縁側でかじったあの甘さと。
スイカは、望にとってただの果物じゃない。
夏の全部を閉じ込めた宝石のような存在だった。
子どもの頃、祖母の家には大きな庭があり、夏になるとスイカを買ってきては井戸水で冷やした。
「井戸で冷やすと冷蔵庫よりおいしいんだよ」と祖母は言い、新聞紙にくるんだスイカをそっと水に沈めた。
手で触って「そろそろいいね」と言う祖母の笑顔が、今も鮮明に浮かぶ。
望は今、都内の出版社で働いている。
忙しい毎日に追われるように、季節を味わう余裕などない日々。
でも、スイカだけは別だった。
六月の終わりから八月いっぱいまで、冷蔵庫にはいつも一切れのスイカが入っている。
朝食に、仕事から帰った夜に、あるいは休日の昼下がりに。
スイカを頬張るその一瞬だけ、望は過去の自分に戻れる気がした。
ある年の夏、望は久しぶりに祖母の家を訪れる決心をした。
祖母は数年前に亡くなり、今は誰も住んでいない。
けれど、どうしてもあの井戸でスイカを冷やしてみたかったのだ。
「もう水、出るかなあ」
そんな不安を胸に、車で三時間かけて祖母の家へ。
鍵は管理をしてくれている地元の親戚に借りた。
久々の家は埃っぽかったが、不思議と空気が優しい。
庭には雑草が生い茂り、井戸も苔むしていた。
それでも、手動のポンプを押してみると、キュッ、キュッという音とともに、しばらくしてひんやりとした水が流れ出た。
思わず、笑みがこぼれる。
スーパーで買ってきた大玉のスイカを新聞紙に包み、そっと井戸水の中へ。
祖母の真似をしながら、「そろそろいいね」と口に出して言ってみる。
縁側に腰掛けて、スイカを切る。
赤い果肉に黒い種がきらめき、まさに宝石のようだった。
ナイフで切り分けたひと切れを頬張る。
しゃりっという音とともに、甘く冷たい果汁が口いっぱいに広がった。
「……やっぱり、おいしい」
思わず、涙が出た。
祖母のこと、昔の夏のこと、忙しくて忘れていた大事な何かが、スイカと一緒に戻ってきたようだった。
帰りの車の中で、望は決めた。
今年はスイカの魅力を伝えるエッセイを書こう、と。
仕事で執筆の機会は少ないが、自分にしか書けないものを形にしたい。
読んだ人が、少しでも夏を思い出してくれたら、それでいい。
数週間後、「スイカの記憶」と題したエッセイは、会社の社内報に小さく掲載された。
反響は思ったより大きく、同僚たちが「読んでスイカ食べたくなった」と笑った。
それからというもの、毎年夏になると、望は必ず一つスイカにまつわる文章を書くようになった。
祖母との記憶、ひとりの夜の味わい、都会の屋上で食べたスイカ割り……スイカは季節の中の宝箱。
切っても、食べても、想いがあふれ出す。
今年も、山下青果の店先にスイカが並ぶ。
望はその丸い果実を手に取って、にっこりと笑った。
「今年も、来たなあ」