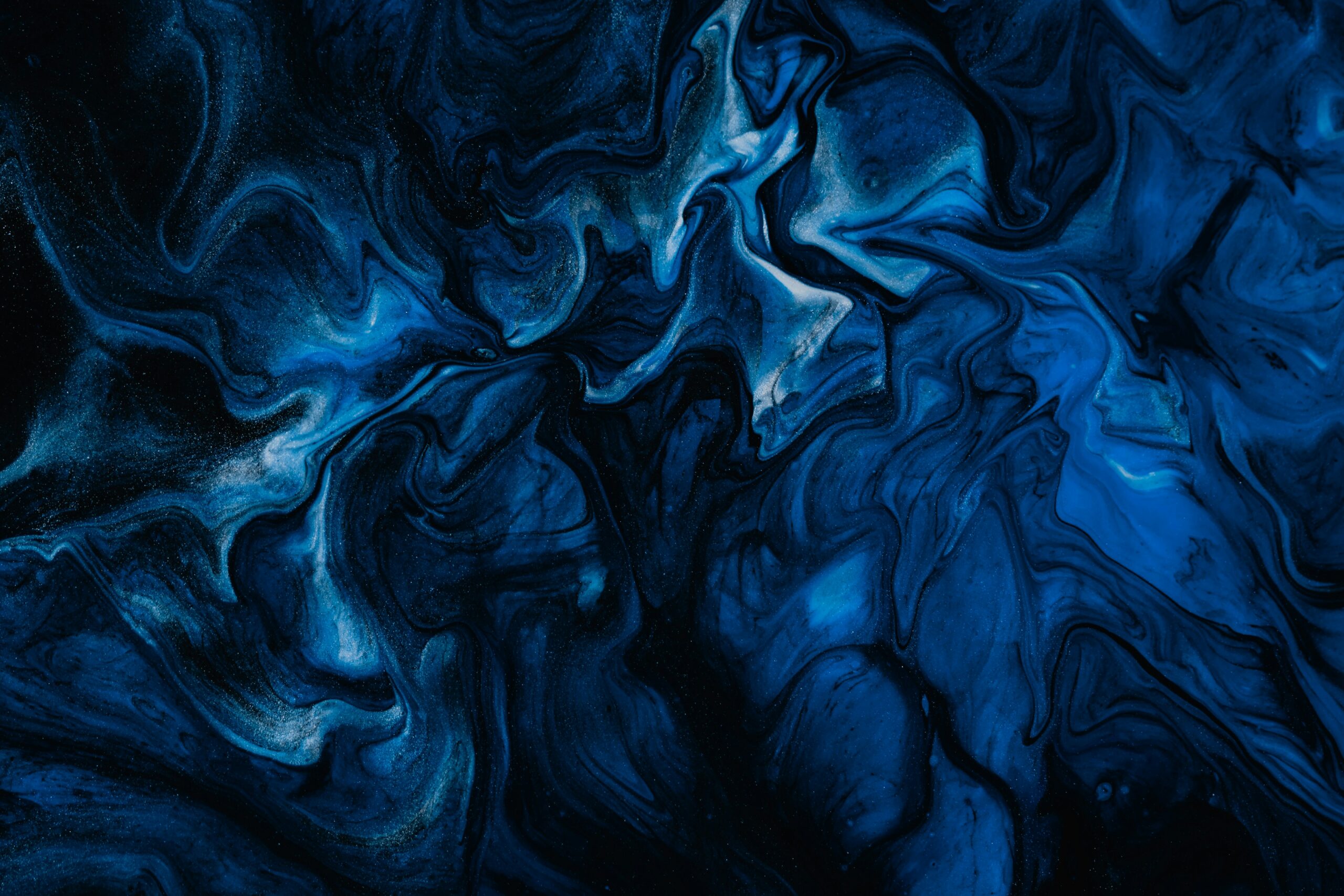青木透は、マーブル模様が好きだった。
絵具を混ぜたときの偶然生まれる模様、珈琲にミルクを垂らした瞬間に広がる流線。
自然が織りなすその不規則な美しさに、彼は心惹かれていた。
透は美術大学で染色を学び、特にマーブル染めに傾倒していた。
だが卒業後は生活のため、普通の染物工場に就職し、規則通りの柄を作る日々が続いた。
それでも、休日には工房を借りてマーブル染めの研究を続けていた。
ある日、透は偶然立ち寄ったギャラリーで、一枚のスカーフに目を奪われた。
美しいマーブル模様が広がるその布には、見たこともない独特な色の流れがあった。
作者の名前は「北条瑞希」とあった。
「この模様……すごい」
透はスカーフを食い入るように見つめた。
色の組み合わせ、流れ、すべてが完璧だった。
どのように染めたのか知りたくなり、ギャラリーのオーナーに尋ねると、幸いにも瑞希の連絡先を教えてもらえた。
数日後、透は瑞希のアトリエを訪ねた。
瑞希は透より少し年上の女性で、長い髪をラフにまとめ、手には染料の跡が残っていた。
彼女は優しく微笑みながら透を迎え入れた。
「マーブル模様が好きな人に会えるなんて嬉しいわ」
アトリエには、さまざまな色合いのマーブル染めの布が並んでいた。
そのどれもが、透の知る技法とは一線を画すものだった。
「この色の流れ、どうやって作ったんですか?」
透が尋ねると、瑞希は微笑みながら答えた。
「自然の流れに任せるのよ。手でコントロールしすぎないことが大事。たとえば、この布は雨の日に染めたもの。湿気が多いと、染料の広がり方が変わるの」
透は驚いた。
彼はこれまで、技法にこだわりすぎていたのかもしれない。
瑞希の作品には、偶然の美しさがそのまま生かされていた。
それから透は何度も瑞希のアトリエを訪れ、一緒に作品を作るようになった。
彼女の考え方に触れるうちに、透の作風も変わっていった。
ある日、透はふと思い出したように瑞希に尋ねた。
「瑞希さんがマーブル模様を好きになったきっかけは?」
瑞希は少し考えた後、懐かしそうに語った。
「昔、祖母が持っていたマーブル模様のノートがあったの。そのノートに、祖母は毎日小さなことを書いていたの。天気とか、庭に咲いた花のこととかね。私はそのノートを眺めるのが好きだった。いつも違う模様があって、でもどこか同じ雰囲気がある。マーブル模様って、人の記憶みたいだと思わない?」
透はその言葉を聞いて、ゆっくりと頷いた。
確かに、マーブル模様は偶然の産物でありながら、ひとつひとつに個性がある。
それはまるで、人の思い出が折り重なるようなものだった。
やがて二人は共同で展示会を開くことになった。
瑞希の柔らかく流れるような作風と、透の精密な色彩の組み合わせは、多くの人を魅了した。
そして展示会の最終日、透は瑞希にそっと言った。
「これからも一緒に、マーブル模様を作っていきませんか?」
瑞希は微笑み、静かに頷いた。
こうして二人は、流れるような模様のように、新しい未来を染めていくことになったのだった。